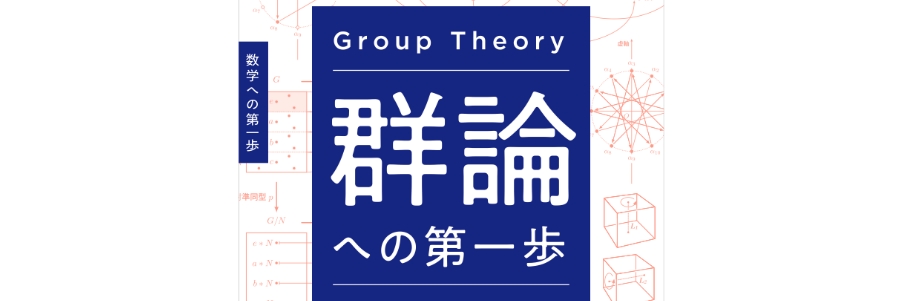
「群論への第一歩」読書レビュー
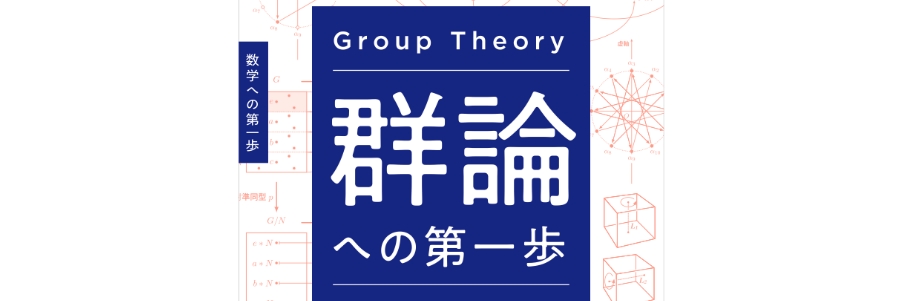
著者の良い部分が消えた.
Section titled “著者の良い部分が消えた.”この著者(結城浩さん)の良さが消えた本である.著者は数学系の本でとても定評があり,売れている. 何が良いのかと言うと,数学的な記述に対してそれがどういうことなのかを一般的な言葉で丁寧に解説し, 読者に示している点である.
しかしこの「群論への第一歩」はどうかというと違う.群論とは一体何なのかという問い(本の中にもそういう記述がある)に, 「群の定義を満たす集合のこと」と答えている.今までの著者ならば,こういった問いにきちんと答えていたと思う. だけれども今回は「定義のとおり」と答えている.良さが失われた部分である.
旧Twitterで著者をフォローしているので,本書を読んだ方が「わかりやすかった」とポストしているのを見る. だが,わたしは異を唱えたい.
本書を読んでいて,説明が丁寧で不明点がないのでわかりやすいが,これは「わかったつもり」になっている. つまり,読んでわかった状態(不明点もないし)だが,少し踏み込んで考えると本当はわかっていなかった状態になるからである. なぜかというと,群の定義がどういう主張なのか,なぜそのような定義なのか意味を解説していないので, 他の参考書を読むと手も足も出なくなるのである.
定義をそのままの意味で使うと問題がある理由を微分で考える.定義は簡単に書くと
である.この分数の極限を微分と決めたが,誰もこの分数の形が微分であることだけで学習を進めない. この微分の意味は一般に「傾き」と理解される.「傾き」を基本概念として学習し,理解できるように本の内容が展開される. 傾きが連続であれば微分可能であるなどが一例である.
群の定義だけ行い,基本理解をせず,その後の定理を説明していることが著者らしくなく,本書の最大の問題点なのである.
群の定義だけ行い,理論を解説するような本はいっぱいある.「群論への第一歩」を読む根拠などない. 私は図書館で借りて半分くらいは読んだが,途中で止めた.他に良い群論の本はあるので.
本書で著者の数学的な限界が見えたような気がした.